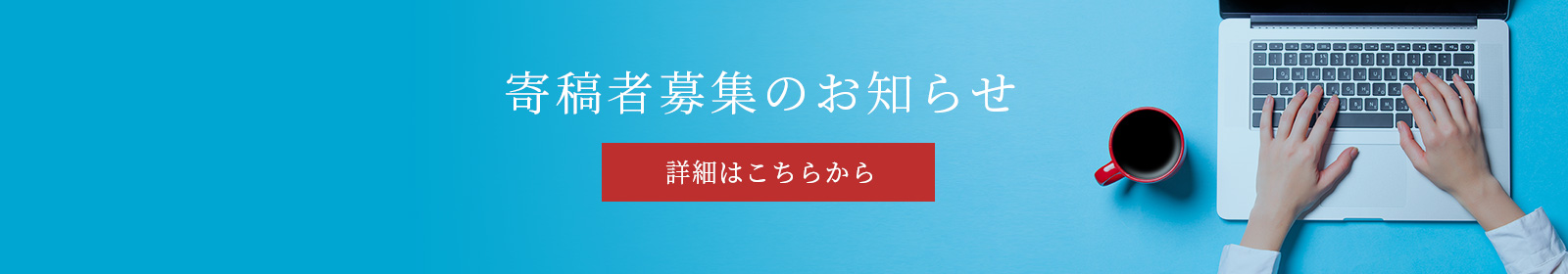この記事の目次
東北地方の伝統工芸品

青森県
津軽びいどろ
元々は漁網を浮かせるために使われている浮き玉を製造していた北洋硝子が、浮き玉の製造で培われた「宙吹き」という技法を用いて作っているのが津軽びいどろです。新しい技術を常に取り入れ、近年では色ガラスを用いて四季を表現するなど、色とりどりの作品が製作されています。
 津軽びいどろの魅力と美しさを歴史から紐解く!
津軽びいどろの魅力と美しさを歴史から紐解く! 津軽塗

青森県で初めて国の無形文化遺産に選ばれた津軽塗。何重にも塗り重ねられた漆を磨いてなめらかにする工程は2ヵ月以上の日数をかけることもあり、これによって複雑でありながら美しい模様と頑丈でしっかりとした肌触りの両立を可能としているのです。
 津軽塗の特徴|青森初の重要無形文化財の良さと魅力に迫る!
津軽塗の特徴|青森初の重要無形文化財の良さと魅力に迫る! 岩手県
岩谷堂箪笥

岩谷堂箪笥は、本体部分から金具部分にいたるまでその全てが手作業で製作されています。非常に重厚で優美な仕上がりは古くから高級和箪笥として支持を得ていたものの、現代の住宅や生活の変化により需要は減少を続けています。
そこで、岩谷堂箪笥組合は新たな消費者のニーズに合わせて「岩谷堂くらしな」というブランドを立ち上げ、伝統の再建を目指しています。
 岩谷堂箪笥の特徴と歴史|作り方やお手入れ方法もチェック
岩谷堂箪笥の特徴と歴史|作り方やお手入れ方法もチェック 南部鉄器

約400年もの歴史を持ち、かつての日本の家庭には南部鉄器の鉄瓶や急須が一つはあったと言われるほどでしたが、今では見かけることはほとんどありません。しかし、南部鉄器の伝統の品々は中国や東南アジア・ヨーロッパにまで範囲を広げ、爆発的な人気を誇っているのです。
「南部鉄器といえば黒」というイメージを覆したさまざまな色合いのカラーポットは、海外から逆輸入され日本でもブームになりつつあります。
 南部鉄器の魅力|サビにくいお手入れ方法も解説!
南部鉄器の魅力|サビにくいお手入れ方法も解説! 秋田県
曲げわっぱ

弁当の見栄えを良くし、具材のおいしさをさらに引き立てると主婦の間で大人気となっているのが曲げわっぱ。
天然の秋田杉から作られる曲げわっぱは、木目の美しさからも大変重宝されています。しかし、2012年に資源保護により秋田杉の伐採が禁止されてしまったため、現状の在庫がなくなると入手することはできなくなってしまいます。
 曲げわっぱ弁当箱のカビはこれで解決!毎日使うのって大丈夫?
曲げわっぱ弁当箱のカビはこれで解決!毎日使うのって大丈夫? 宮城県
鳴子漆器
1660年代から続く伝統の塗り立て技術は、見た目の美しさと頑丈さを両立させた鳴子独自の技術です。一般的な木地呂漆塗りや拭き漆塗りはもちろん、鳴子漆器独自の技法「龍紋塗り」も職人の手によって伝承され続けています。
 宮城伝統こけしの特徴と歴史|鳴子漆器と木地玩具のコラボもご紹介
宮城伝統こけしの特徴と歴史|鳴子漆器と木地玩具のコラボもご紹介
関東地方の伝統工芸品

栃木県
益子焼

意外と歴史は浅く、江戸時代末期から製作の始まった益子焼は、独創的なデザインと手に入りやすい価格帯から日常使いの食器として重宝されてきました。現代でも若手からベテランにいたるまで幅広い世代の陶芸家が多種多様な作品を作り続けています。
 益子焼の特徴|美しさはその歴史にあった!
益子焼の特徴|美しさはその歴史にあった! 千葉県
房州うちわ
房州地方は女竹の産地であったため、房州うちわは漁師町の女性や高齢者にとって手ごろな内職として発展を遂げていきました。また、柔軟性のある女竹を用いて作られた房州うちわは丈夫でありながらしなやかな仕上がりをしており、日本三大うちわの一つとして現代にまで受け継がれています。
 日本三大うちわ「房州うちわ」「京うちわ」「丸亀うちわ」の魅力に迫る!
日本三大うちわ「房州うちわ」「京うちわ」「丸亀うちわ」の魅力に迫る! 茨城県
笠間焼
茨城の伝統工芸品である笠間焼は、伝統にこだわらず自由に作れるという気風を求めて全国各地から若い陶芸家が集まり作られたため、「特徴がないことが特徴」と言われています。しかしこれは、魅力がないからというわけではなく、製造工程に縛りがないため作り手によってさまざまなデザインの笠間焼に変貌するからです。
 笠間焼は特徴がないのが魅力!?その良さを深掘り
笠間焼は特徴がないのが魅力!?その良さを深掘り 東京都
江戸切子

「江戸切子」はガラスの表面に紋様を施して作られるガラス工芸品です。切子と名の付くものは薩摩切子などほかにも存在しますが、江戸切子を名乗れるのは江戸切子協会組合に指定された特定の地域で作られているものだけ。
高い品質と美しさを追求し続ける江戸切子は、地域ブランドとして発展を続けています。
 江戸切子の良さ|使いやすさと魅力を歴史に学ぶ
江戸切子の良さ|使いやすさと魅力を歴史に学ぶ 神奈川県
鎌倉彫

カツラやイチョウの木で作られる鎌倉彫は、温もりを感じさせながら陰影のある彫りの深い味わいと漆による深い色調が特徴。中国より渡ってきたその技術は、800年たった今でも伝統を守りながら色あせることなく受け継がれています。
 鎌倉彫の良さと特徴|美しさはどう作られる?歴史もご紹介!
鎌倉彫の良さと特徴|美しさはどう作られる?歴史もご紹介!
中部地方の伝統工芸品

石川県
九谷焼

彩り豊かなデザインと美しい絵付が評価され、皇室に献上されてきた歴史を持つ九谷焼。山水や花鳥などの伝統的な絵柄も大変な人気がありますが、近年では数々のキャラクターとコラボしたマニアックな商品も作られています。
ウルトラマンやガンダムなど、自身の好きなキャラクターとコラボしているか探してみるのも楽しいかもしれません。
 九谷焼の特徴|キャラクターとのコラボも魅力!
九谷焼の特徴|キャラクターとのコラボも魅力! 加賀友禅

500年ほど前に加賀の国で生まれた加賀友禅は「加賀五彩」と呼ばれる、
- 藍色
- 臙脂(えんじ)色
- 黄土色
- 草色
- 古代紫色
の5色で構成された美しい色合いが魅力。また、ほかの地域で製造されている友禅に比べて手作業の工程が多く残されていることも特徴の一つです。
 加賀友禅の特徴と魅力|その美しさを歴史に学ぶ
加賀友禅の特徴と魅力|その美しさを歴史に学ぶ 輪島塗

人口3万人ほどの小さな町である輪島市で作られる輪島塗は、日本海を使った貨物輸送や旅客輸送が活発であったことや行商人や職人が全国行脚で販売をしていたことなどから全国的に広まっていきました。
また、現代でも100を超える工程を手作業で行っており、11の職種に分業されながらも伝統技術は継承され続けています。
 輪島塗の歴史と特徴・良さ|一生使えるのも魅力!
輪島塗の歴史と特徴・良さ|一生使えるのも魅力! 山中漆器

山中漆器は、良質な木材を求めて移住してきた職人集団の手によって作られます。その技術は山中温泉とともに発展し、美しい山中高蒔絵の手法は磨かれていきました。
また、伝統的な漆器作りだけではなく、合成樹脂による合成漆器の生産やPET樹脂による給食食器の作成・バイオマス樹脂の導入など、さまざまな試みによって伝統漆器の生産額は全国一位をキープし続けています。
 山中漆器(山中塗)の特徴|輪島塗との違いってなに?
山中漆器(山中塗)の特徴|輪島塗との違いってなに? 岐阜県
美濃焼

美濃焼は岐阜県の土岐市・多治見市などの東濃エリアで製作されている陶磁器の総称。そのため「美濃焼」という焼き物は正確には存在しておらず、代表的なものには志野焼(しのやき)や織部焼(おりべやき)などがあります。
また、美濃焼は日本の焼き物のうち半分以上のシェアを占めているため、私たちにとって身近な焼き物であると言えます。
 美濃焼の特徴|その魅力をじっくりと解説
美濃焼の特徴|その魅力をじっくりと解説 愛知県
瀬戸焼

1000年以上の歴史を持つ瀬戸焼。陶磁器全般を指す言葉「せともの」の語源となっていることからも分かるとおり、日本国内で広く流通して親しまれています。また、ウィーン万博で出展されるなど海外へも活躍の場を広めています。
 瀬戸焼の特徴と由来|せとものの意味と捨て方は?
瀬戸焼の特徴と由来|せとものの意味と捨て方は? 常滑焼

「急須といえば常滑焼」と言われるほど絶大な人気を誇る常滑焼。ほかの急須で入れたお茶と比べて、まろやかな口あたりがとてもおいしいと評判です。3000基以上にもなる穴窯を持ち、日本六古窯の一つにも数えられる常滑焼は、お茶好きには欠かせない逸品です。
 常滑焼の良さと美しさ|その魅力と特徴を解説
常滑焼の良さと美しさ|その魅力と特徴を解説 富山県
高岡銅器
富山県の高岡市で作られる高岡銅器は、日用品として使われるだけでなく仏具や銅像としても手がけられており、そのシェアは95%にもなると言われています。
また、誕生から400年を迎えた2011年を節目として新たなブランド「KANAYA」を立ち上げ、現代のライフスタイルに合う製品を提供し続けています。
 高岡銅器の魅力|特徴と新ブランドの4種類の商品もご紹介!
高岡銅器の魅力|特徴と新ブランドの4種類の商品もご紹介!
近畿地方の伝統工芸品

京都府
京うちわ
京うちわは、うちわの面と柄を別々に作り、後から柄を差し込んで完成させる「挿し柄」という独特の構造をしています。京うちわの絵柄は、金箔(きんぱく)をあしらったものから美しい四季を表現したものまで絵師の手によって描かれます。
房州うちわや丸亀うちわと並んで「日本三大うちわ」と評されるほど、その美しさは大人気になっています。
 日本三大うちわ「房州うちわ」「京うちわ」「丸亀うちわ」の魅力に迫る!
日本三大うちわ「房州うちわ」「京うちわ」「丸亀うちわ」の魅力に迫る! 京焼・清水焼
京都で焼かれていた京焼と清水寺山道近辺で焼かれていた清水焼が総称して「京焼・清水焼」と呼ばれています。伝統工芸品として指定されている名称も京焼・清水焼です。後継者不足や低価格化による問題で一時期は伝統の継承が途切れてしまう恐れがあったものの、海外進出や近代的な生産手法を取り入れることで再び輝きを取り戻しつつあります。
 京焼・清水焼の歴史と特徴|多彩な美しさと良さのルーツをたどる
京焼・清水焼の歴史と特徴|多彩な美しさと良さのルーツをたどる 西陣織
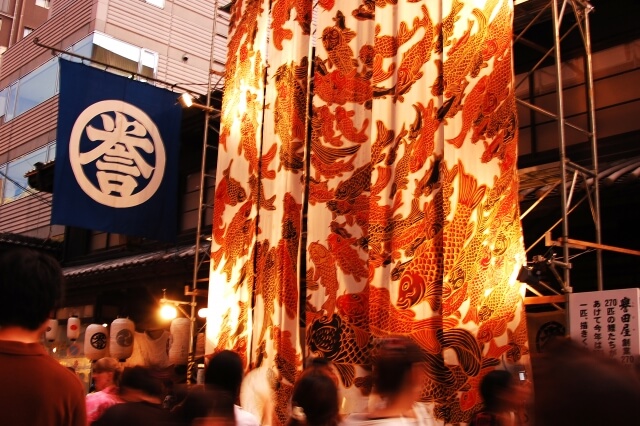
応仁の乱の後、西軍が本陣としていた場所「西陣」で職人が集まり織物をしていたことから西陣織と名付けられました。日本最高峰と名高い織物である西陣織は、シャネルやルイヴィトンなど海外のさまざまなトップブランドとのコラボも実現し、変化を続けています。
 西陣織の魅力と特徴|美しさ・良さの秘密は作り方にあり
西陣織の魅力と特徴|美しさ・良さの秘密は作り方にあり 滋賀県
信楽焼

商売繁盛の縁起物として飲食店などに置かれていることが多く、信楽焼のことを知らなくともタヌキの置物のことなら知っている人も多いでしょう。2017年には日本遺産にも選ばれるなど、「わび・さび」の趣を伝承しながら現代へと発展を遂げています。
 信楽焼の特徴と良さ|たぬきの置物の意味ってなに?
信楽焼の特徴と良さ|たぬきの置物の意味ってなに?
中国地方の伝統工芸品

岡山県
備前焼

釉薬を使用せず絵付けもすることなく焼かれる備前焼は、土本来の色合いと味わいを感じられることが最大の特徴。1200度以上にもなる温度で10日ほどかけてしっかりと焼かれているため、強度がとても強く保湿性にも優れています。
 備前焼の特徴は?|良さと魅力・代表的な種類も紹介
備前焼の特徴は?|良さと魅力・代表的な種類も紹介
四国地方の伝統工芸品

香川県
丸亀うちわ
丸亀うちわが作られている香川県丸亀市は、日本におけるうちわの生産量において約90%のシェアを誇る日本一のうちわ産地です。形やデザインも多様で年間一億本もの量が生産される丸亀うちわは、心も体も涼しくなること間違いなしです。日本三大うちわにもなっています。
 日本三大うちわ「房州うちわ」「京うちわ」「丸亀うちわ」の魅力に迫る!
日本三大うちわ「房州うちわ」「京うちわ」「丸亀うちわ」の魅力に迫る! 徳島県
大谷焼
大谷焼は、貯蔵や醸造する際に用いられる身の丈ほどの大甕(おおがめ)や睡蓮鉢など大型の陶器が有名で、これらを焼き上げている登り窯のサイズは日本一の大きさとも言われています。また、作る際に行われる「寝ロクロ」という技法も大谷焼独自の技法として継承されています。
 大谷焼の良さ|コラボも魅力の陶器の特徴をご紹介
大谷焼の良さ|コラボも魅力の陶器の特徴をご紹介 愛媛県
砥部焼
陶磁器の中では優れた耐久性を持ち、ひび割れや欠けが入りにくいという特徴を持つ砥部焼。夫婦げんかで投げつけたとしても割れないといういわれから別名「喧嘩器」とも呼ばれています。
技術の進歩や若手作家・女性作家が進出したことによってポップでカラフルなデザインの砥部焼も増え、女性を中心に人気を集めています。
 砥部焼の特徴|デザインが魅力の愛媛磁器の歴史に迫る
砥部焼の特徴|デザインが魅力の愛媛磁器の歴史に迫る
九州・沖縄地方の伝統工芸品

鹿児島県
博多織

2018年に777周年を迎えた博多織。日本三大織物の一つにも数えられ、徳川将軍家に献上されていた歴史を持つことから献上博多とも言われています。華やかで美しくもありながら綿密で丈夫な生地に織り上がっているため、激しい動きの多い男性用の帯として重宝されてきました。
 博多織の特徴と歴史|人気グッズもピックアップ!
博多織の特徴と歴史|人気グッズもピックアップ! 薩摩切子
薩摩切子は、ガラスに着色を施した色つきのガラスが特徴。特に、日本で初めて作られた紅色のガラスは「薩摩の紅ガラス」と称され、大変評価の高いものでした。
しかし、1858年に薩摩切子の生みの親である島津斉彬(なりあきら)が急死し、1863年の薩英戦争による侵攻によってガラス工場はほとんど焼失、1877年にはその技術は完全に途絶えてしまいます。幻となった薩摩切子は1985年、職人の手によって約100年ぶりに復元され、今日にいたるまで復刻・創作が行われています。
 薩摩切子の特徴と歴史|江戸切子との違いも解説!
薩摩切子の特徴と歴史|江戸切子との違いも解説! 本場大島紬

奄美大島を生産地とし、日本を代表する「着物の女王」とも言われる本場大島紬は、世界三大織物の一つにも選ばれています。製織が終わるまでに1年以上を要し、大変な手間をかけて作られるものもあるため、持っているだけでもその人のステータスシンボルとなるでしょう。
 大島紬の特徴と魅力|歴史や作り方と気になるお値段も紹介!
大島紬の特徴と魅力|歴史や作り方と気になるお値段も紹介! 福岡県
小石原焼
「用の美の極致である」と絶賛される小石原焼。「飛び鉋(とびかんな)」や「刷毛目」と呼ばれる技法を用いて規則的に模様を描くことで、整いながらも温かみのあるデザインをしています。今も昔も変わらぬ技法で作られる小石原焼は、日本各地で愛され続けています。
 小石原焼の歴史と特徴|その良さを同じ福岡の高取焼とともに解説
小石原焼の歴史と特徴|その良さを同じ福岡の高取焼とともに解説 佐賀県
有田焼

有田焼は、国内で初めて作られた磁器として、日常使いの品から装飾品までさまざま様式を持っています。ほかの伝統工芸品同様、生活環境の変化により売上や後継者の減少に悩まされていましたが、佐賀県にある16の窯元と16組のデザイナーが協力して新たなブランド「二ーゼロイチロク(2016)プロジェクト」を立ち上げ、有田焼の変革を行っています。
 有田焼の特徴|良さと魅力を創業400年の歴史に学ぶ
有田焼の特徴|良さと魅力を創業400年の歴史に学ぶ 長崎県
三川内焼
軍港の町として栄えていた長崎県佐世保市の三川内で作られている三川内焼は、幕府や天皇への献上品として知られています。早くからオランダや中国への輸出も行っており、繊細で優美な仕上がりは今もなお海外を魅了し続けています。
 三川内焼の特徴と歴史|別名「平戸焼」の魅力と良さとは?
三川内焼の特徴と歴史|別名「平戸焼」の魅力と良さとは? 波佐見焼

元々は波佐見市で有田焼として作られていましたが、産地厳格化の流れから「波佐見焼」と呼ばれるようになります。おしゃれで使いやすいデザインから、さまざまなブランドが参入して新しい器が次々と作られるようになり、その人気は確立されていきます。
 波佐見焼の特徴とは?魅力や歴史を深掘り!
波佐見焼の特徴とは?魅力や歴史を深掘り! 大分県
別府竹細工

別府竹細工は、室町時代に行商用の籠として作られたのが始まりと言われています。別府温泉の名が広まったことで土産として持ち帰られるようになり、全国へと広まっていきました。別府市では今でも竹資源の確保や伝統技術の保護・継承に取り組みながら、竹細工の歴史を刻んでいます。
 別府竹細工の魅力と美しさの秘密|作り方と歴史も一緒に解説!
別府竹細工の魅力と美しさの秘密|作り方と歴史も一緒に解説! 沖縄県
琉球ガラス

戦後に在留米軍が飲み終えたコーラやビールの使用済みガラス瓶を再生することでガラス製品を作っていたという背景から、本来なら不良品として処分されているような気泡や厚みがあるビンも風変わりなデザインとして活用されていました。それが、琉球ガラスの始まりです。
 琉球ガラスの美しさと魅力|特徴のルーツはその歴史にあり?
琉球ガラスの美しさと魅力|特徴のルーツはその歴史にあり?
これらのほか、地域百貨では記事として紹介していないものの、北海道ではウロコ彫りが特徴的な浅い木製のお盆「二風谷イタ」と、オヒョウという落葉高木などの樹皮の内皮から作られた糸を使って織られた反物の「二風谷アットゥシ」が伝統工芸品になっています。
日本の伝統工芸品の中には、素晴らしい技術や歴史を持ちながらも、需要の低下や高齢化による後継者不足が原因でほとんど生産されなくなったものも多く存在します。何世代にもわたって受け継がれてきた伝統工芸品に改めて関心を持つと同時に、手に取ってみてはいかがでしょうか。