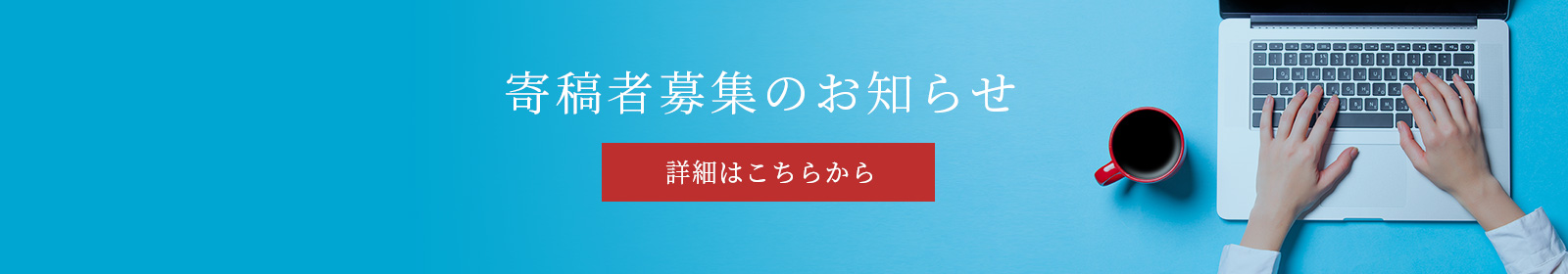この記事の目次
水力発電のデメリット

水力発電とは
水力発電は水車を基本とする技術で、水が流れている時の運動エネルギーや、水が高い所から低い所へ流れる高低差の位置エネルギーを使って発電用のタービンを回して発電します。電力需要のピークに合わせて発電所を運転・停止できるため、電力供給量の調整用電源として用いられています。
ダムを建設する場合には大きな労力を要する
小規模な発電設備でも発電できるのが水力発電の特徴ですが、ダムを必要とする大規模なものは建設に時間とコストがかかり、周辺に対する環境の影響も大きいという理由から新しい発電所の建設が進まず、全電力に対する水力発電の割合はあまり多くありません。
また、渇水時に発電できないなど気候の影響を受けやすいことや、ダムに溜まった土砂を排出する必要があるなど、メンテナンスが必要といったデメリットもあります。
ゴミの処理が必要
ダムを建設する場合は、土砂や流木だけではなくゴミの流入も発電の障害になります。
元々これらは焼却処分されていましたが、環境問題への関心の高まりとともに分別リサイクルへと変わっており、特に流木を破砕して木片にしたチップは良質の燃料となります。
周辺で利用できる水量との兼ね合いがある
水力発電設備の建設を難しくしているのは環境影響のほかにもあります。それは水利権です。水力発電では河川の水をバイパスして使うので、それまで周辺住民が利用していた水量が減ってしまいます。そのため、河川には維持流量という基準が設定されており、発電所が使える水量を規制しているのです。
水力発電のデメリットの解決策

日本は水力発電に適した国土があるものの、土地の水没など広範囲の開発行為がともなう水力発電用のダム建設は狭い国土にとって不向きです。そこで、大規模な水力発電の開発により発生する課題の解決に向けた取り組みを紹介します。
環境への取り組み
環境省は、ダム建設による森林伐採などの環境影響を減らす取り組みとして、
- ダム建設では湛水面積100ヘクタール以上
- 水力発電所では出力3万キロワット以上
の場合を環境アセスメントの対象としています。
地域復興への取り組み
水力発電による地域復興の例として福島の取り組みを紹介します。
東日本大震災で壊滅的被害を受ける前は原子力発電により首都圏へエネルギーを供給していた福島県ですが、既存のダムの潜在力を発揮させ、再生可能エネルギーを増強することを目的とする「福島水力発電促進会議」を発足させ、水源地域である福島を復興に導く取り組みを行っています。
この取り組みでは、まず助成金を活用して既存のダムのかさ上げなどの整備を実行して発電量を増加させます。そして、増えた電力の売り上げを森林整備や環境整備観光施設整備、雇用創造事業に利用して地域を復興させるというものです。
比較的簡単に始められる小水力発電
小水力発電は小規模なので、
- 特定の事業者だけではなく小規模な事業者でも参加できる
- 用水路など水利権の発生しない場所に設置できる
- ダム建設などの大きなコストを必要としない
という特徴を持つ発電設備です。
小水力発電に明確な定義はありませんが、1万kw~3万kw以下を中小水力発電と呼ぶことが多いです。また、新エネルギー法(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法)によると、水力発電設備の規模による分類は下表のとおりになります。
| 区分 | 発電出力(キロワット) |
|---|---|
| 大水力 | 100,000 以上 |
| 中水力 | 10,000 ~ 100,000 |
| 小水力 | 1,000 ~ 10,000 |
| ミニ水力 | 100 ~ 1,000 |
| マイクロ水力 | 100 以下 |
小水力発電の分類
小水力発電は、大規模水力発電の小型化ではなく独自の技術で、どこにでも設置が可能です。その分類は簡単にまとめると以下のようになります。
- 水路式:川をバイパスして水路を設置し、落差を確保する
- 直接設置式:既存の堰(せき)(水をせき止めることを目的として、河川や湖沼などに設けられる構造物)などに水車と発電機を設置する
- 減圧設備代替式:水道の給水設備などにある減圧弁の圧力差を利用する
- 現有施設利用:現有のプールなどを利用する
小水力発電が導入可能なエリア
落差と流量があればどのような所にも設置可能な小水力発電は、一般河川や砂防ダム・治山ダム以外にも、農業用水路や上水道施設・下水処理施設、さらにはダム維持放流、既設発電所の放流水、ビルの循環水・工業用水などに設置されています。具体的には以下のような発電所が稼働しています。
- 蓼科発電所:2011年6月稼働。老朽化により休止した発電所の再利用。発電出力260kw
- 百村発電所:2006年4月稼働。既存水路の落差のある部分に設置。発電出力30kw×4基
- 上水道施設に設置した例:2011年4月稼働。利水ダムから浄水処理場までの落差を利用。発電出力35kw
- ビルの循環水・工業用水に設置した例:2008年5月稼働。ビル内の空調機に使われる冷却水が使用後に上層階から地下水槽に落ちる落差を利用。発電出力7kw
また、環境省の「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書(2011年4月)」によると、中小水力発電の賦存量と導入ポテンシャルは下表のとおりになります(単位はkw)。
| 賦存量※1 | 導入ポテンシャル※2 | |
|---|---|---|
| 河川部 | 1,655 | 1,398 |
| 農業用水路 | 32 | 30 |
| 上下水道・工業用水道 | 18 | 16 |
| 合計 | 1,705 | 1,444 |
※コストや法制度、地形などを考慮した場合の開発可能なエネルギー量
2050年までの水力発電の導入見込み量(地球温暖化対策に関する中長期ロードマップ)では、3万kW以下の中小水力発電の導入ポテンシャルを全て開発することを目標としています。
水力発電の方式別のメリット・デメリット

水力発電は水の流れる勢いや水の落下(高低差)を利用して発電されますが、その方式は主に4つに分類できます。自然の水循環のエネルギーを利用するため、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しないというメリットがありますが、ここではそれぞれの発電方式のメリットとデメリットを見ていきたいと思います。
さらに、5つ目として小水力発電のメリットとデメリットも記載しています。
流れ込み式(自流式)
流れ込み式(自流式)は、川の水をそのまま発電機に流す方式です。建設コストが比較的安く収まるというメリットがあるのですが、発電量自体が川の水量と比例するためにその量を調整できないことと、雨の多寡といった天候の影響をそのまま受けてしまうことがデメリットになります。
調整池式
調整池式は、調整池(1日~1週間の流量調整用)に蓄えた水を発電機に流す方式です。発電量が調整できて天候の変化にも対応できるものの、建設にコストと時間を要することがデメリットになります。
貯水池式
貯水池式は、貯水池(年間または季節の流量調整用)に蓄えた水を発電機に流す方式です。調整池式と同様に発電量を調整できるのと天候の変化に対応できるのがメリットですが、建設にコストと時間を要することに加えて周辺地域に水没の可能性が発生するなど、建設地への影響をより慎重に検討しなければならないことがデメリットです。
揚水式
揚水式は、発電所の上部に作った調整池に蓄えた水を発電機に流す方式です。発電に使った水を発電所の下部に作った調整池に貯め、電力使用量の少ない夜間に火力発電所の電力を利用して下部の調整池から上部の調整池に揚水し、再利用します。
発電の際だけでなく水をくみ上げる際にもエネルギーのロスが発生するというデメリットがあるものの、夜間の余剰電力を水エネルギーの形で蓄えて日中の需要が高い時間帯に転用できるというメリットがあります。
小水力発電
メリットとしては、小水力発電の多くは流れ込み式や水路式のためダムを必要とせず環境負荷が小さいことや、小規模なため、NPOや個人が主体になれることがあります。さらに、出力変動が少なく安定的で稼働率が高いことや設置面積が小さくて済むことも経営的なメリットと言えるでしょう。
デメリットは、改善されつつあるものの、水利権がつきまとう場合の申請手続きが煩雑なため個人や小事業者には大きな負担となることや、設置場所がさまざまなため落差と流量に合わせた機器をそのつど開発する必要があることなどが挙げられます。
水力発電に適した国土を持つ日本ですが、新たなダム建設をともなう発電所建設は、その環境影響の大きさや国土の狭さの点から困難とされています。しかし、新たな技術開発で実現した小水力発電は、その経済性と法的課題を解決することで、持続可能なエネルギー源としてさらに浸透していく可能性があるでしょう。