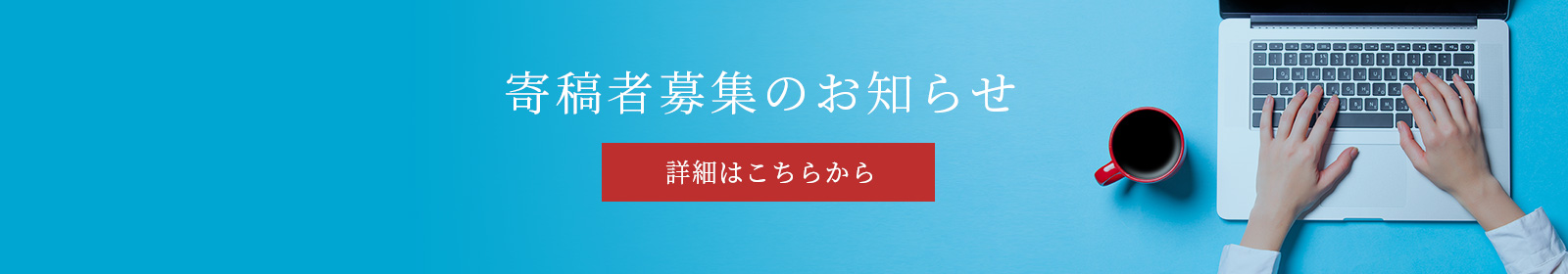この記事の目次
ゼロエミッションとは

持続可能な経済活動や生産活動の手法
ゼロエミッション(排出ゼロ構想)とは、1994年に国連大学が提唱した、人間の活動から発生する廃棄物を限りなくゼロにすることを目指しながら最大限の資源活用を図り、持続可能な経済活動や生産活動を展開する理念と手法です。
ゼロエミッションは社会全体で取り組まなければ実現しないもので、廃棄物をゼロにするところから取りかかるのが一般的です。
しかし、本来の定義としては、単に排出を抑えるだけではなく、資源の有効活用やリサイクルの促進を行うことで社会の仕組みそのものを変革していく取り組みであることも重要です。
ゼロエミッションの実現のために必要な条件
ゼロエミッションを実現させるためには、ざまざまな産業が連携する仕組みを形成していく必要があります。例えば、ある産業から排出された廃棄物・副産物を、ほかの産業が有効活用することで資源を無駄なく社会全体へと循環させる、という形です。
しかし、廃棄物をゼロにしても化石燃料に頼って二酸化炭素を出すのであれば、ゼロエミッションが真に達成されたとは言えません。同時に資源循環にも取り組まなければならないのです。
そのためには、
- 廃棄物を排出しにくい原材料を使用する
- 環境を汚染してしまう恐れのない生産工程を用いる
- 廃棄物の活用時に、通常の生産工程よりも多くのエネルギーを必要としない
ことが重要となります。
リサイクル法が足がかりに
循環型社会の構築やゼロエミッションに向けてさまざまな取り組みが行われていますが、その足がかりとなったのが1991年に制定されたリサイクル法(資源の有効な利用の促進に関する法律)です。
これによって、廃棄物の適正な処理を目指していた行政が有効なリサイクルを目指す方針へとシフトし、以後、多くの製品についてのリサイクル法が制定されています。
- 容器包装リサイクル法:容器包装にまつわる分別収集および再商品化の促進などに関する法律
- 家電リサイクル法:使用しなくなった家電製品において、資源の有効利用を推進するための法律
- 食品リサイクル法:食品循環資源の再生利用などを促進するための法律
- 建設リサイクル法:建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律
- 自動車リサイクル法:使用済自動車の再資源化などに関する法律
- 小型家電リサイクル法:使用済小型電子機器などの再資源化を促進するための法律
川崎ゼロエミッション工業団地の取り組み
その後、2000年には循環型社会形成推進基本法が制定されました。この基本法に基づいた取り組みとして、エコタウン事業(地域の環境調和型経済社会形成のための地域振興策)があります。
1997年、川崎市は川崎臨海部全体(約2,800ヘクタール)を対象とした「環境調和型まちづくり構想」を策定し、エコタウン事業の国内第1号として政府からの支援を受けました。
この川崎エコタウン内にある川崎ゼロエミッション工業団地は、個々の企業から出る廃棄物を可能な限り抑制するとともに、以下のような企業間の連携で再資源化とエネルギーの循環利用を行っています。
- 天然ガス自動車の使用
- 工場内での水力発電設備の使用
- 工業薬品と水の循環使用
- 難再生古紙(色物、ラミネート紙など)のリサイクル
- メッキ廃液を工場外に排出しない循環クローズドメッキシステム
ゼロエミッションの具体例

2021年には世界で約8,000万台(四輪車)が販売され、世界に12億台以上が存在すると言われる自動車の排出ガスをゼロにする取り組みが、ゼロエミッション車規制です。
大気汚染物質を出さないゼロエミッション車
ゼロエミッション車とは、搭載された動力源から
- 微粒子
- 炭化水素
- 一酸化炭素
- オゾン
- 鉛
- 窒素酸化物
- 硫黄酸化物
- 二酸化炭素
などの大気汚染物質を出さない自動車(ZEV:zero emission vehicle)のことを指します。温室効果ガスを排出しないため、排出物「ゼロ」の扱いとなるのです。
また、具体的には自転車や電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)がZEVの定義に当てはまります。
徐々に普及が進む
現状、自転車以外のゼロエミッション車は導入コストが高いため、急速には普及は進んでいません。コストダウンを図るには、従来型のボディー設計を流用できるパワートレインパーツの設計が必要になるからです。これは、一般自動車に使用されている従来のガソリンエンジンと同じ大きさにすることなどで、それらと共通の生産ラインを使用することが可能になるためです。
とはいえ、ゼロエミッション車推進のための取り組みは
- リチウムイオンによるバッテリーの生産
- 使用済みバッテリーのリサイクルと二次活用
- 急速充電器の設置と充電インフラの整備
- 充電方式の統一化
など継続的に進められており、購入台数も徐々に増えています。
なお、電気自動車・燃料電池車・コンパクトリチウムイオンバッテリー車に使われるバッテリーの世界シェアは、2014年時点で1位が日本、2位が韓国となっていましたが、近年では中国や韓国が上位を占める構図になっています。
ZEV規制の広まり
ZEV規制とは、1990年にカリフォルニア州内で施行された一定台数以上を販売する自動車メーカーを対象にZEVを一定比率(14%)以上販売する義務を課すと定めたものです。
カリフォルニア州が公共交通に乏しい車社会であり、地形的に大気汚染を起こしやすいという特徴を持っていることから、全米に先駆けて導入されました。
また、同様の取り組みには以下もあります。
- 欧州(イギリス、フランス):2040年までに新車販売のZEV率100%を目指す
- インド:2030年までに新車販売のZEV率100%を目指す
ZEV規制の本来の目的は自動車全体の排気ガスのゼロを達成することですが、目標を達成できなかった企業は罰金を支払うか他社から権利を購入しなければならなかったため、既存の自動車メーカーから激しい反発があり、
- プラグインハイブリッド車(PHEV)
- ハイブリッド車(HV)
- 天然ガス車(NGV)
- 低燃費ガソリン車
もZEVに準ずるとされました。
ゼロエミッションに向けた取り組み:サーマルリサイクル

環境問題で3Rといえば「リデュース・リユース・リサイクル」ですが、そのうちのリサイクルは「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」に分けられます。
また、循環型社会形成推進基本法では、この3Rに優先順位をつけて
- 1.リデュース(発生抑制)
- 2.リユース(再使用)
- 3.リサイクル(再生利用)
- 4.サーマルリサイクル(熱回収)
- 5.適正処分
としています。
 「循環型社会」と「3R」〜これからの地球を守るために〜
「循環型社会」と「3R」〜これからの地球を守るために〜 サーマルリサイクルとは
サーマルリサイクルとは、使用済みの資源を燃焼させてその熱を利用することを指します。つまり、資源を熱に変えて再利用することです。
このサーマルリサイクルに関しては、「安易な焼却処分につながるサーマルリサイクルはリサイクルではない」とする意見と「リサイクルにかかるエネルギーや化学物質の環境負荷を考えるとサーマルリサイクルの方が良い」とする意見との賛否両論があります。
サーマルリサイクルの概要・詳細
サーマルリサイクルには、
- ゴミ発電のようにそのまま燃焼させる方法
- 固形燃料化する方法
- 高炉でコークスの代わりに原料兼熱源として利用する方法
があり、固形燃料化については大きく以下の2つに分けられます。
- RDF(Refuse Derived Fuel):家庭が排出する可燃ゴミが主原料
- RPF(Refuse Paper & Plastic Fuel):企業が排出する古紙およびプラスチックが主原料
また、廃棄物を燃焼させてサーマルリサイクルを行った際に出る焼却灰をセメント原料として利用する「エコセメント」は、歩道のブロックなどに利用されています。
ここで、サーマルリサイクルに使われる熱源に目を向けてみます。主にサーマルリサイクルが行われている製品として、木材パレットとパチンコ台があります。
木材パレットは繰り返し再使用された後にサーマルリサイクルされる良い例ですが、パチンコ台はマテリアルリサイクルを行う仕組みがあるにもかかわらずサーマルリサイクルが行われている不適切な例です。
できる限り多くの製品が、
- 発生抑制長期使用により廃棄物とならない
- 再使用循環して利用する
- 再生利用形を変えて利用する
- 熱回収燃料として利用する
という正しい順序で運用されていくことが、効果的な環境保全・ゼロエミッションにつながっていきます。
世の中から廃棄物を完全にゼロにすることは難しいことなのかもしれません。しかし、廃棄物を減らす・リサイクルする、ということを私たちが日常的に意識していくことで、少しずつゼロエミッションに近付いていけるのではないでしょうか。