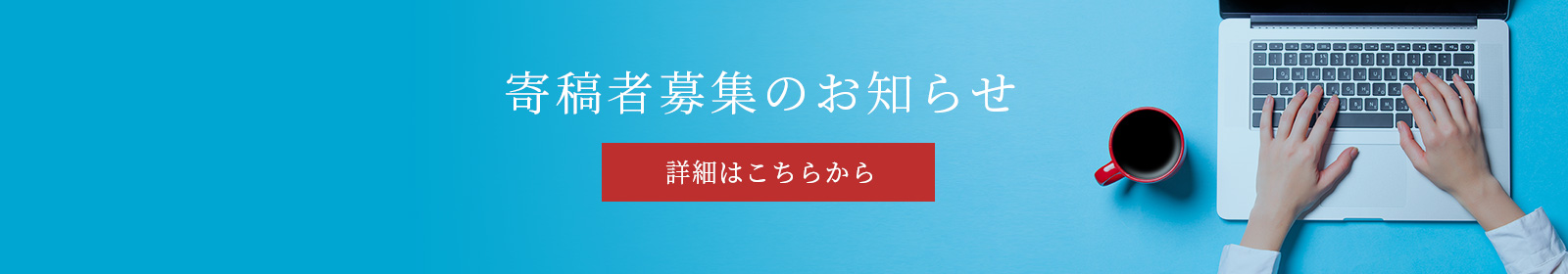この記事の目次
梅ジュースで食中毒ってホント?

自宅で簡単にできて美味しい梅ジュース。梅自体が酸っぱいため殺菌効果もありそうで、食中毒には縁遠いようにも思えますが、実は保存方法や作り方を誤ってしまうと梅が腐ってしまう可能性があるのです。
まずは、食中毒になってしまう可能性のある梅ジュースの見た目や味、臭いについて簡単に覚えていきましょう。
カビが生えていたり梅に白い点が付いている
梅シロップから出ている梅に白カビが発生しているものは危険なサインです。同様に、シロップの中に浮いている白い物体も白カビの可能性があります。
また、青カビや黒カビ・赤カビが発生している場合もあり、食中毒の危険があるため、その場合は残念ながら飲まずに捨てるのが安心です。
強い酸味や苦み・刺激臭がする
一般的な梅ジュースに比べて大きく異なる酸味や苦みが感じられる場合も、梅が腐っている可能性を疑ってください。こちらも同様に食中毒になってしまう危険があるため、すぐに外に吐き出して口の中をゆすぎ、梅ジュースは処分しましょう。鼻を突く腐敗臭やシンナー・生ごみのような臭いと表現されることがあります。
食中毒の原因

梅ジュースの食中毒について具体的に見ていく前に、一般的な食中毒の原因を考えていきます。
食中毒を引き起こす原因と考えられているのは、細菌とウイルスの二つ。どちらも肉眼で確認することができない小さいものです。
細菌は増殖しやすい温度と湿度があり、条件がそろってしまうと食べ物の中で増殖。それを食べることで食中毒へと発展します。一方のウイルスは、細菌のように食べ物の中では増殖しないものの、食べ物を経由して体内へと進行すると腸内で増殖し、食中毒へと発展します。
細菌が原因の場合
細菌によって引き起こされる食中毒は、食べ物が腐りやすい夏場に発生することが多いです。代表的な細菌には、
- 腸管出血性大腸菌
- カンピロバクター
- サルモネラ属菌
- セレウス菌
- ブドウ球菌
- ウエルシュ菌
などがあります(詳細は下記参照)。
細菌の多くは、人間の体温(35度~37度)くらいの温度が最も速いスピードで増殖します。
例えば、O157の場合は、7度~8度くらいで増殖が始まり、35度~40度が一番活発になります。また、湿気を好むことも多いため、気温が比較的高くて湿気も高い梅雨時は、食中毒予防を徹底する必要があるでしょう。
ウイルスが原因の場合
一方で、細菌とは異なり低温で乾燥した環境下が長く生存しやすいのがウイルスです。そのため、冬場に発生することが多いです。代表的なウイルスにはノロウイルスがあり、調理者から食品を介して感染したりカキなどの貝類から直接感染したりします。
また、感染によって大規模化することが多いため、年間に発生する食中毒件数の5割以上はノロウイルスが原因の食中毒です。
細菌やウイルス以外にも、毒キノコやフグが保有している自然毒やアニキサスを含む寄生虫なども食中毒の原因となり得ます。
6つの細菌と1つのウイルスによる食中毒

食中毒を引き起こす細菌とウイルス。そのなかでも注意すべき6つの細菌と1つのウイルスについて紹介していきます。
腸管出血性大腸菌
牛や豚など家畜の腸内に存在している病原大腸菌の一つで、代表的なものにO157・O26・O111があります。
非常に毒性の強いベロ毒素を出し、
- 腹痛
- 出血をともなう腸炎
- 水のような下痢
などの症状が出ます。
生肉を食べたり加熱が不十分なまま食べたりすることで発症しやすいです。また、幼児と高齢者は重症化しやすく、最悪の場合死に至るケースもあります。
カンピロバクター
動物の腸内に生息している細菌で、腸管出血性大腸菌と同様に生肉を食べることで感染します。また、猫や犬のふん便にも含まれていることがあるため処理する際には注意が必要です。
初期症状は、
- 頭痛と発熱
- 筋肉疲労
- 倦怠(けんたい)感
などで、そこから腹痛・下痢に発展します。
サルモネラ属菌
動物の腸内から河川・下水まで自然界に広く分布している細菌です。最も身近な細菌で、2500以上の血清型(種類)が見つかっています。
食べ物に付着したサルモネラ属菌を食べてしまうと約半日~2日で吐き気や嘔吐(おうと)・胃腸炎・激しい腹痛・下痢などの症状が出ます。
セレウス菌
土の中や水の中などに広く存在している細菌のため、土の中で栽培される穀物・豆類・香辛料が主な感染源です。
毒素の種類によって、「嘔吐(おうと)型」「下痢型」の二つの症状に分けられます。
- 嘔吐(おうと)型は食後1時間~5時間後
- 下痢型は食後8時間~16時間後
で症状が出ます。セレウス菌は熱に強く、加熱による殺菌が難しいものの、大量に摂取しなければ発症はしないため、菌を増やさないように気を付ければ予防ができます。
ブドウ球菌
人間の皮膚やのどにも分布しているブドウ球菌。調理者の手に傷がある場合などには、食品へ感染する可能性が高くなります。また、熱にも乾燥にも強い性質を持ち、酸性・アルカリ性のどんな環境においても増殖するため、感染させると非常にやっかいな細菌です。
感染した食品を食べると、だいたい3時間で吐き気や下痢が発症します。
ウエルシュ菌
動物の腸内から自然界にまで広く生息している細菌です。酸素がない場所でも増殖し芽胞(がほう)を作ります。
だいたい食後6時間~18時間で発症し、腹痛や下痢が発症します。カレー・ラーメンのスープ・煮魚のように煮込み料理が原因となることが多いです。そのため、残った食品は常温で長期間放置せずに速やかに冷却保存する必要があります。
再加熱をする場合には、じっくりと全体に火を通して早めに食べるようにしましょう。
ノロウイルス
人の手や食品を介して体内に入り、腸内で増殖することで腹痛や嘔吐(おうと)・下痢などを引き起こします。
ノロウイルスに感染しているカキを十分に加熱しないまま食べてしまったり、感染した井戸水を飲んでしまったりすることで発症するほか、ノロウイルスに感染している人に接触され、二次感染するケースも考えられます。
梅ジュースで食中毒にならないための作り方・保存方法
青梅はしっかりと水気を取り、ビンもよく乾燥させる
梅シロップを作る過程で青梅を水で洗いますが、その際、必ずキッチンペーパーなどの清潔な紙・布類で一個ずつしっかりと水気を取るか、天日干しで乾かしましょう。保存瓶も、雑菌が入るのを防ぐために同様にしっかりと水気を取ってください。できれば煮沸消毒をするのがベターです。
これは、上述したカビが好む条件の一つになっている水分をシャットアウトするためです。
冷暗所か冷蔵庫で保存
食中毒にならないように梅ジュースを作れた後は、保存方法にも注意しましょう。直射日光が当たる環境はカビが繁殖しやすい温度になってしまう可能性があるため、ずばり冷暗所に置きましょう。そうすることで最大で1年間保存できるようになります。つまり、開けないままでいれば来年のシーズンまで持つというわけですね。
開封した後は、冷蔵庫に小分けして保存するとよいでしょう。その後は1カ月程度を目安に飲み終えた方が安全です。
食中毒予防の三原則

細菌による食中毒を予防するための方法として、
- 付けない
- 増やさない
- やっつける
という三原則があります。
細菌を付けない
人が生活していくうえで、手にはいろいろな雑菌が付着します。食中毒を引き起こす細菌とウイルスを食品に付けないようにするには、手を洗うことはとても大切になってきます。
- 料理を行う前
- トイレに行った後
- ペットと触れ合った後
- 食事をする前
などは必ず手を洗うようにしましょう。
また、食材を切る時も、生の肉や魚を切るまな板と野菜を切るまな板は別にするなど、できる限り菌が付着しないように行い、使用の都度きれいに洗うようにしましょう。
焼き肉や鍋を食べる際には、生肉をつかむための菜箸と、食べる際に使う箸とで別のものを用意しましょう。
細菌を増やさない
細菌は高温多湿な環境を好むため、食品に付着した菌を増殖させないためには低温保存することが重要となります。
一般的に細菌は、10度以下になると増殖がゆるやかになり、マイナス15度を下回ると完全に停止します。生鮮食品を購入した際には、できるだけ早いうちに冷蔵庫や冷凍庫に保存するようにしましょう。
ただし、冷蔵していても菌の増殖はゆるやかに進行しているため、早めに食べることは大事です。
細菌をやっつける
基本的に細菌のほとんどは加熱することで死滅します。そのため、しっかりと火を通していれば食中毒になる心配はほとんどなくなります。
また、まな板や包丁などキッチン用品に付いた細菌に対しても熱は有効で、洗剤で洗った後に熱湯殺菌すると良いでしょう。
食中毒による腹痛や嘔吐(おうと)・下痢などの症状は、体内から細菌を排除しようとする防御反応です。医者の診察を受けないまま、市販の薬をむやみに服用すると症状が余計に悪化する恐れもあります。
梅ジュースに限らず食中毒の可能性が少しでもある場合には、早めに病院へ行き、医者の診察を受けるようにしましょう。