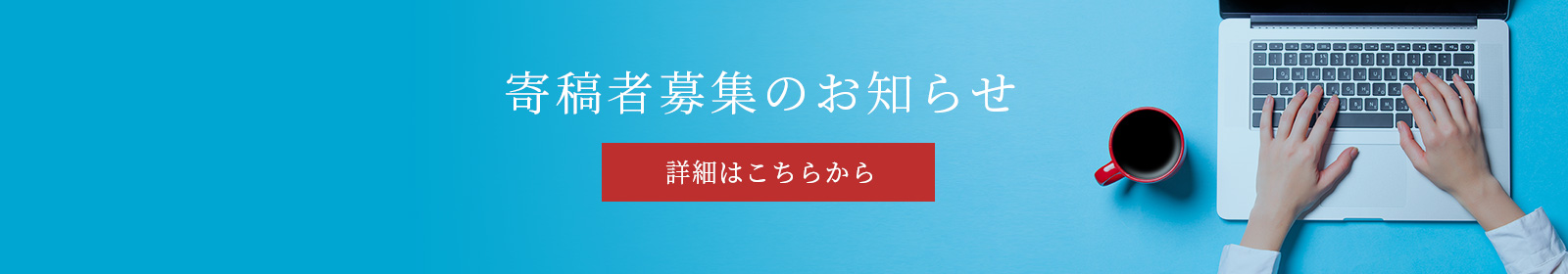この記事の目次
日本の農業の問題点:人手不足

急速な担い手不足
農林水産省が行った調査(農業センサス)によると、2019年の農業就業人口は前年比で約4.1%ダウンの168万人でした。200万人を割って192万人となった2016年から、さらにその人数は減少しています。
1990年には480万人以上いたことを考えると、いまやその数は3分の1にまでなりました。関心の強さほど若者の就農率も高くなく、就労者の高齢化にともなう離農も進んでいることから、農業の担い手は日に日に減少しているためです。
耕作放棄地の増加
高齢化による離農などでいったん農業が行われなくなってしまい、耕作放棄地になってしまうと、その土地の生産能力を十分に回復させるのに多くの時間と手間を要します。
例えば、石垣を組み上げたり土を盛って固める棚田は、それらが崩れないように頻繁に管理を行う必要があります。しかし、耕作放棄をされた場合、災害などなんらかの原因で石段が崩れると、石垣の間に入り込んだカニなどが土を掘り起こしたり、固めた土に雑草が生い茂って土が柔らかくなるなどして、土嚢(どのう)としての機能が失われてしまうのです。
このような状態になるのを防ぐために「棚田オーナー制度」という取り組みも行われていますが、農業従事者の高齢化という根本的な問題は解決できていないなど、課題を残しています。
 棚田オーナー制度のデメリットとメリット
棚田オーナー制度のデメリットとメリット
日本の農業の問題点:技術や作物の偏重

過度な機械化による悪影響
高度経済成長期における日本の農業は機械化や科学の進歩によって著しく発展を遂げていきましたが、それにより豊かな土地が痩せてしまい、さらには農作物の汚染や畜産公害、自然破壊や石油に依存した農業の定着化などの問題も引き起こしました。
そうならないためにも、最低限の農業機械を用いて効率よく作業したり、農薬や化学肥料に頼らないオーガニック農法を採用したりすることで、水と土壌・木々などの貴重な資源を守り、環境保全を重視した農業を目指していく必要性も訴えられています。
また、自然環境保護の動きが活発化してきた日本において、省エネを重視した技術の推進も重要になるでしょう。
- 太陽エネルギー・水力を含む再生可能エネルギーの利用
- 農業機械利用の効率化など、エネルギーの有効利用
- 肥料・農薬を節減した栽培体系の確立
はもちろんのこと、糞尿を有効活用するコンポストトイレの開発、堆肥の発酵熱を利用した野菜作りもすでに実用段階に入っています。このように、自然循環型社会に沿った農業への取り組みは順調に進められています。
作物の技術バランスの悪さ
また、高度経済成長の際に栽培を拡大するよう指定された作物の米・畜産品・野菜・果物については技術的にも大きく発展した一方で、指定されなかった作物の麦・大豆・穀物・飼料作物については技術の停滞が続いています。
今後の日本農業を支えていくためには、このような偏った技術発展を改め、お米や畜産品に注力した分と同様の努力を、麦・大豆・穀物・飼料作物にも注ぐことが必要になってきます。
ただ、上記作物の発展の遅れをすぐに取り戻すのは容易ではありません。現状、技術的に発展させるための最大の問題は、国内の栽培に最も適した品種を特定化することだと言われています。
国内品種と外国品種をまとめて試験・研究が行われているものの、問題の解決には至っていません。栽培技術の体系をとってもまだまだ課題は山積みです。
農業の人手不足の解決策はある?

高まる若者の農業への関心
農業人フェアを開催すると多くの若者が参加をするなど、若者の農業への関心意欲は高まってきています。
その背景として考えられるのは、出世したりお金を稼いだりすることへの意欲の低下や、仕事で社会に貢献したいという気持ちの高まりなど、近年の仕事に対する考え方の変化も関係しているでしょう。
とはいうものの、新規に農業を始める若者の数はあまり増えていません。日本の新規就農者数は2007年には7万3000人程度だったのに対して、2017年度は5万5000人程度と年々減少を続けており、49歳以下の人数はわずか2万700人と半分にも満たない数値です。
この数値からも分かるとおり、農業を始める人の多くは定年退職後に実家へと戻り、農業を継ぐというケースなのです。
しかしその一方で、
- 農業法人に属して農業を始める「新規雇用就農者」
- 農業の出身者が身近におらず、完全に新規で農業を始める「新規参入者」
に関しては、49歳以下の割合が7割以上を占めています。
ただ、それでも新規就農者全体の19%ほどにしかならないため、まだまだ少ないのが現状です。
 農業法人化のデメリット|費用やメリットについても調査!
農業法人化のデメリット|費用やメリットについても調査! 若者が就農しない理由
政府は、40代以下の就農者数を増やすために、青年就農給付金などさまざまな制度を確立しており、一時的ではあるものの新規参入者の数は順調に増加の傾向にあります。特に、青年就農給付金が導入された2012年には、1180人から2170人と約二倍の成長を遂げています。
しかし、給付金や補助金の影響で就農者が増えたとなれば、その期限が切れてしまった際に離農率が高くなってしまうのではないか、という懸念もあります。今後も、新規就農者の数を増やすための取り組みを考えていかなければなりません。
例えば、若者の就農人口が増えない理由の一つに労働環境の厳しさがあります。個人農家のほとんどは土日の休みがなく、収入も不安定です。就農の1年目~2年目の時点で農業の所得のみで生計が成り立っている人は全体のわずか14%しかいません。
そのため、新規就農者の3割ほどの人は数年以内に離農してしまっています。
収入は良いのでは?
農家の仕事は、
- お米・野菜・果物のような農作物を作る
- 牛を育てて酪農・畜産を行う
などさまざま。畑や牧草地を作るためには土地や機械なども必要になってくるため、初期投資だけでも1000万円ほどはかかってしまいます。そのため、初期費用を回収するだけでもかなりの期間を費やしてしまう恐れもあるのです。
また、農業で収入を得ている人の年収平均はだいたい300万円だと言われています。なかには、600万円稼いでる人もいれば1000万円という高年収の人もいます。育てている農産物や規模によっても金額に大きく差が出てくるためです。
年収300万円以上が農業で稼げているとなれば、十分な生活水準を得られるのではと思うかもしれません。しかし、実際にはこれだけの収入を必ずしも確保できるわけではありません。なかには、年収が数十万円にしかならない人もいます。
農業で高収入を獲得している人は、
- 品種改良によって専用のブランド農作物を作り出した
- 新技術を導入したことで低コストでの栽培を実現した
- 災害による被害を受けにくい農作物を開発した
など、さまざまな努力の上に成り立っています。
最近では、スーパーマーケットなどには卸さず、インターネットで直接販売して利益率を増やす、などの新しい営業システムを確立した農家も多くあります。今後は、農作物をただ作るのではなく、加工・販売までを自分で行う6次産業化も重要な手段になっていくかもしれません。
 6次産業化のメリット・デメリット|失敗事例もビジネスモデルのヒント
6次産業化のメリット・デメリット|失敗事例もビジネスモデルのヒント
農業に対する関心意欲が高まり、新たに農業を始める若者が増えている一方で、新規就農者数は年々減少傾向にあります。
農業がいかに魅力的な職業であるかを若者に実感してもらうためにも、広報活動を広く行いながら、農業を取り巻くさまざまな課題についても取り組んでいかなければなりません。