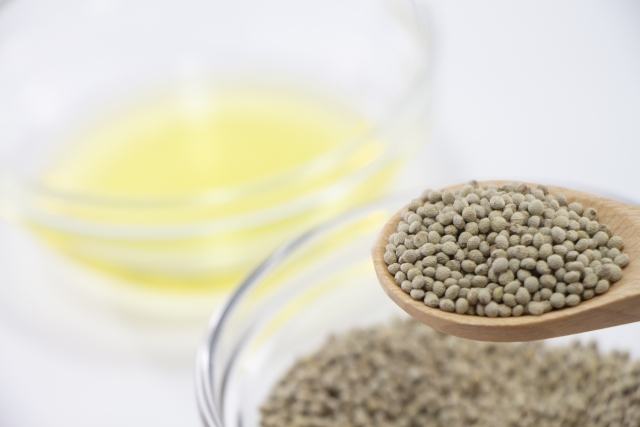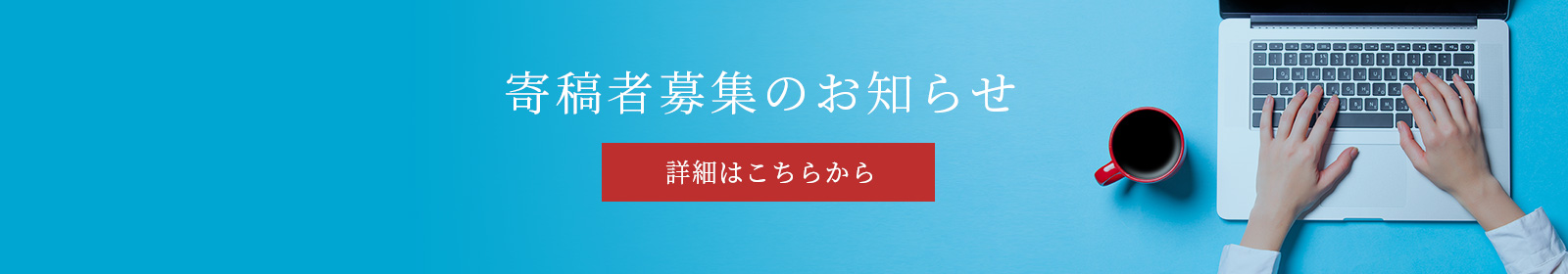この記事の目次
えごま油とは

「10年長生きできる」と言われるほどの栄養価の高さ
「えごま」は、別名「ジュウネン」とも呼ばれ、青ジソ(大葉)とよく似た葉を持つシソ科の植物です。えごまを食べると10年長生きできると言われ、その栄養価の高さは昔から注目されてきました。また韓国では、キムチにして漬け込んだり生葉のまま肉を巻いて一緒に食べたりとお馴染みの食材でもあります。
栽培する際は5月~6月の新緑のころに種を蒔きます。9月下旬から10月ごろに花を咲かせ、同時に油の原料となる米粒より少し大きいくらいの実が付きはじめます。
えごまの実を搾ると「えごま油」となりますが、実のままでもおいしくいただくことができ、岐阜県の飛騨高山では五平餅にえごまの実をすりつぶしペースト状にしたタレを付けて食べる文化もあります。
亜麻仁(あまに)油との違い
メディアで「えごま油」とよく比較されるものが「亜麻仁(あまに)油」です。効果は後ほど紹介するえごま油と大きな差はありませんが、えごまがシソ科の植物であることに対し、亜麻はアマ科の植物の実を原材料として使用していることに違いがあります。
えごまは比較的温暖な地域での栽培に適しているため日本各地で栽培が行われているのに対し、亜麻は寒冷な地域を好む植物です。国内においては北海道で栽培や加工がされていますが、まだまだ日本では馴染みの薄いものと言えるでしょう。
ごま油との違い
「えごま油」に「ごま」の文字が含まれているため、えごま油がごま油の仲間だと思われる方もいるかもしれませんが、亜麻仁油と同様、全くの別ものです。えごまがシソ科の植物であると言いましたが、ごまはゴマ科の植物。植物の分類も違えば、栄養成分も違うため、得られる効果も異なります。
必須脂肪酸が摂取できる
えごま油に含まれる代表的な成分がアルファリノレン酸(オメガ3脂肪酸)です。これは体内に入るとEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)といった青魚に豊富に含まれている成分に変化します。また、これらは「必須脂肪酸」と呼ばれる体内では作り出すことができない栄養素で、食品から効果的に摂取しなければ摂り入れることができない重要な成分です。
近年の日本人の食生活は魚や野菜よりも肉や炭水化物を多く摂るように変化していったため、「アルファリノレン酸」は不足しがちな成分の代表格とも言えます。
アルファリノレン酸はほかの食用油にも含まれていますが、その含有量はえごま油が圧倒的。以下はアルファリノレン酸が含まれる食材の比較です。アルファリノレン酸を摂取するためには、えごま油を上手に使用することがポイントだと分かりますね。
アルファリノレン酸の含有量
- えごま油(100g):24,000mg
- なたね油(100g):7,500mg
- 大豆油(100g):6,100mg
- オリーブ油(100g):600mg
- ごま油(100g):310mg
- くるみ(100g):9,000mg
- さんま1尾(150g):220mg
えごま油の効果

えごま油に含まれるアルファリノレン酸は、体内に入ることでEPAやDHAに変化し、以下のような効果をもたらします。
血流改善・血栓予防
EPAやDHAには血液をサラサラにする効果があるため、動脈硬化や心筋梗塞、高血圧や糖尿病を防いだり、脳の働きを高める効果があります。
アレルギーの抑制
花粉症や皮膚炎などのアレルギーの原因の一つであるリノール酸に対してアルファリノレン酸は競合的に働くため、アレルギーを抑制する効果があります。
老化予防
アルファリノレン酸は細胞壁を構成する重要な成分のため、摂取することで細胞壁が構成され、老化の進行を抑制する効果が期待できます。また、ガンになりにくい体を作れるという研究もあります。
認知症やうつの緩和
EPAやDHAが老化やストレスで鈍っていた脳の神経細胞を再び活性化させ、脳の血流を良くし、認知症やうつを予防・改善する効果があります。さらに、精神を安定させる効果があるとも考えられています。
ダイエットにも
アルファリノレン酸にはほかにも、代謝を活発にすることで脂肪を燃焼し、その結果、脂肪が蓄積されにくい体作りに効果があるとも言われています。
さらに、えごま油に含まれるポリフェノールの一種「ローズマリー酸」に糖質の吸収を抑える働きがあるため、同様にダイエットに向いているという声もあります。
えごま油のおいしい食べ方

熱を加えないメニューがベスト
さまざまな効果があるえごま油は、シソが原料ということもあり、多少の青臭さやシソの香りの強さなどが感じられます。非常に特徴的な食用油のため、使用することに抵抗がある人も多いのが実情です。
また、主成分であるアルファリノレン酸は酸化しやすいという特徴があります。酸化は熱を加えると進行するため、150度以上の熱で加熱してしまうと味の劣化はもちろん、重要な栄養素が欠如してしまう恐れもあります。
そのため、熱を加えないドレッシングや味噌汁、スープの香り付けとして使用することがおすすめの食べ方です。
食べすぎに注意
豊富なアルファリノレン酸を含むため多く摂取したくなりますが、摂り過ぎると腸が活発に動き腹痛や下痢を引き起こします。また、100gあたり900kcalと油の中では比較的低カロリーなのですが、ダイエット効果を期待して多く摂取することもおすすめできません。
保存時の注意点
アルファリノレン酸は酸化しやすいという特徴のため、光や熱、金属、空気と触れる時間が長いとすぐに劣化してしまいます。冷蔵庫や冷暗所で保存し、開封後はなるべく早く、できれば1カ月以内に使い切るとおいしく効果的に食べられます。
おすすめのえごま油
えごま油の効果や注意点を説明してきましたが、ここでは比較的使いやすいサイズ感であり、かつ酸化しにくい容器にこだわったえごま油のおすすめ商品をご紹介します。
【商品紹介】あぶらやマルタ えごまオイル 180g
注ぎ口も少しずつ出るように工夫が施されているため、スープなどに少量かけたいときにもおすすめできる商品です。
富山市が進めるえごまの取り組み

最後に国内での地域活性の取り組みとして富山県富山市が進めている「エゴマで進む6次産業化」を紹介します。
えごまの特産品化に向けて
富山市は2011年に「環境未来都市」に選定された地区であり、えごまの特産品化のプロジェクトはその一環として2012年にスタートしました。
富山市西部には、現在ではスキーや温泉といった観光地としても知られる、古くから信仰の山として登られてきた牛岳という山があります。そこで、この牛岳の恵みによって湧き出る温泉熱を利用してえごまを栽培するという全国でも類のない画期的なプロジェクトが話題となりました。
着々と進む6次産業化
2012年5月に「牛岳温泉熱等を活用した農業の6次産業化」プロジェクトがスタート、同年8月には「エゴマの葉・実・油による一体的な6次産業化」の方向性が確立され、地元の有力企業の共同出資のもと、えごま生産・加工に加えてえごまの利用や消費の振興を行う「健菜堂」が立ち上がりました。
2013年には健菜堂が中心となり、市内の80近くの団体・個人とえごまの利用普及のための共同グループを運営。えごまを使用した特産品の開発を進めているほか、2015年には牛岳の温泉熱や太陽光を活用した植物工場を竣工し、生産・加工・販売までを一体的に行う事業を展開しています。
2018年、富山市においてはさまざまなえごまを使用した商品の開発が進んでおり、今後の取り組みにも注目が集まっています。
今回はメディアでも話題のえごま油を紹介しました。日々の健康のために活用してみてはいかがでしょうか。さらに気になる方は、富山市の取り組みにもぜひ注目してみてください。