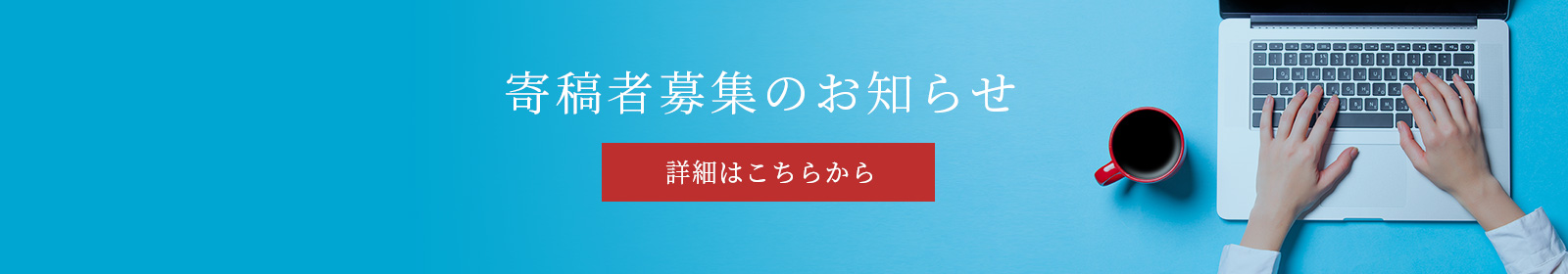この記事の目次
世界自然遺産「小笠原諸島」
小笠原諸島は、東京から南に1000㎞離れた太平洋上にある日本の領土で、父島、兄島、弟島、母島、姉島、妹島、聟島(むこじま)、嫁島、媒島(なこうどじま)など、30以上の島々で構成されています。
この小笠原諸島は、誕生してから一度も大陸と地続きになったことがないため、独自の進化を経た固有生物が魅力の一つとなっています。
世界遺産になるまでの軌跡
世界自然遺産に登録されるためには、「自然景観」「地形・地質」「生態系」「生物多様性」のうちいずれかひとつで類いまれな価値があると認められなければなりません。小笠原諸島の主だった特徴は下記になります。
地形・地質
約4800万年前の太平洋プレートの沈み込みがきっかけで「無人岩」という特殊なマグマが形成され、父島・聟島となりました。この無人岩は世界最大と考えられています。
また、次のような形成過程の異なる島が集まっていることも、小笠原諸島の地形・地質を類いまれなものとしています。
- 火山活動によって形成された母島
- サンゴ礁の発達によって形成された石灰岩地帯にある南島
生態系
過去に一度も大陸と地続きになったことがない小笠原諸島では、生態系に独自の種分化が起こっており、数多くの固有種が見られます。天然記念物に指定されている哺乳類のオガサワラオオコウモリをはじめ、植物の3割以上、陸産貝類の9割以上が固有種となっています。
生物多様性
多様な起源の種が混在していて、複数の絶滅危惧種の生息・繁殖地域ともなっている小笠原諸島の生物多様性は、世界的にも重要な地域として類いまれな価値を持っています。
小笠原諸島の魅力
小笠原諸島の生態系は確かに類いまれな価値を持っていて、それだけでもこの島々を訪れる理由として十分ですが、自然景観を楽しめるスポットも多く存在します。
- 父島大村海岸:サラサラの砂浜とブルーの海でゆったりと過ごせる素敵な海岸
- 中山峠:コバルトブルーの海と緑の森のコントラストが絶景
- 小笠原海洋センター:アオウミガメの日本最大の繁殖地である小笠原諸島において、その保護・繁殖を行っている施設
小笠原諸島の生態系

小笠原諸島は元々、陸上生物のいない島でした。流木に乗ってきた生物、気流に乗ってきた生物、長距離を移動してやってきた鳥、鳥に運ばれてきた生物など、長い時間をかけて偶然たどり着いた植物や動物が独自の生態系を作り上げていったのです。
小笠原諸島に生息する固有種
固有種の宝庫である小笠原諸島について、どのような固有生物がいるのか少しだけ紹介します。
- 大きなシダ植物のマルハチ、小さな花を付けるシマホルトノキ
- 草食の哺乳類であるオガサワラオオコウモリ
- オガサワラトカゲ、ミナミトリシマヤモリの2種類の両生類
- アシガラカラスバトやメグロ、オガサワラノスリなどの鳥類
- ハナダカトンボやオガサワラシジミなどの昆虫類
「カタツムリの楽園」とも
小笠原諸島は「カタツムリの楽園」とも呼ばれることがあります。カタツムリ(陸産貝類)の固有種率はなんと93%で、ハワイ、ノーフォーク島、ガラパゴスに次ぐ4番目の多さとなっています。
小笠原諸島にはおよそ100種類の固有種カタツムリがいます。
カタマイマイ属は、餌や捕食場所、休眠場所によって殻の形状・色彩に違いが現れます。樹上性の種類の殻は背が高く小型、半樹上性の種類は扁平、地上性の種類は背が高くなります。
また、カタツムリはあまり移動しない生物であるため、場所によっては10m離れただけで別の種類になってしまうこともあります。
- ヌノメカタマイマイ:殻長19ミリメートル、殻径23ミリメートル程度、殻は固くて厚さがあります。地中性で、母島・向島・姉島の高標高地帯に生息しています。
- アケボノカタマイマイ:殻径22ミリメートル程度、殻には3本の濃紫褐色の色帯があります。地表性、母島北部・中部の低標高地帯に生息しています。
- ヒメカタマイマ:殻長13ミリメートル、殻径16ミリメートル程度、殻は薄く淡黄褐色から濃褐色までさまざま。樹上性、母島北部の高標高地帯に生息しています。
- コガネカタマイマイ:殻径24ミリメートル程度、殻は色は黄、黄白、橙、褐色、黒褐色などで、1~3本の色帯があります。地表性、母島南部に生息しています。
外来種により崩れる小笠原諸島の生態系

世界自然遺産となった小笠原諸島では現状の生態系を維持することが求められており、守るべき固有種の状況調査と外来種の駆除が行われています。
グリーンアノールの影響と対策
1960年代から父島に定着したグリーンアノール(南米原産、イグアナ科)は、ペットとして持ち込まれたものが遺棄されたという説や、米軍の物資輸送とともに侵入したなどの説があります。
この外来トカゲは、固有種であるオガサワラシジミ、オガサワラトンボを含む在来昆虫を食べ、絶滅に近い状態にしています。また、在来種のオガサワラトカゲとは食物が競合しており、在来トカゲの個体数を著しく減らす原因ともなっています。
この外来トカゲのコントロールが世界自然遺産登録の条件となり、2006年からはゴキブリ捕りのような粘着式ワナを使用した捕獲が行われています。
捕獲作戦の結果、部分的にではあるもののグリーンアノールの個体数が減り、固有生物を増やすことに成功した地域もあります。ただ、根絶に向けては新しい捕獲方法の開発が必要となっています。
ノヤギ・ノネコの影響と対策
ノヤギは、かつて食用として持ち込まれたヤギが野生化したもので、島の植物を食べ尽くす恐れがあります。また、植物が食べ尽くされた後のむき出しになった土壌が雨により海に流出し、サンゴ礁に悪影響を与えるという連鎖も起こっています。
父島以外ではノヤギの根絶に成功しており、父島でも根絶作業を続行中です。しかし、ノヤギは在来種と外来種を区別なく食料としていますので、ノヤギを駆除すると外来植物が増加してしまうという問題も抱えています。
ノネコは、ペットやネズミ駆除用に持ち込まれたネコが野生化したものです。鳥類を食物としており、固有種のアカガシラカラスバトなどに被害が出ています。
そこで2005年にノネコの捕獲が始まり、全島的にノネコの低密度化に成功。捕獲したノネコは本土へ搬送して獣医師会がペット化し、飼い主を探して引き渡しています。
クマネズミの影響と対策
クマネズミは、船にまぎれて入り込んだと言われています。植物の種子や果実を食物としているため、植生に影響を与えます。
2008年からヘリコプターによる薬剤散布で駆除が行われており、その効果により植物の回復、海鳥の繁殖、カタツムリの回復傾向が見られます。しかし一方で、クマネズミの駆除は、これを食物としているオガサワラノスリ(絶滅危惧種)の生存に悪影響を及ぼすため、慎重に進められています。
ニューギニアヤリガタリクウズムシの影響と対策
ニューギニアヤリガタリクウズムシは、沖縄から移入された樹木に付着して、1990年代に父島に生息を始めました。
この外来生物は肉食性プラナリアの一種で、小笠原諸島では主に陸産貝類を捕食しています。そのため父島では固有のカタツムリが激減しています。
ニューギニアヤリガタリクウズムシは駆除自体がほぼ不可能とされているため、固有種の生息地を囲い込み、父島以外に広げない取り組みによって固有種の保全が行われています。
外来種の植物の影響と対策
1876年3月に日本の領有が確定した小笠原諸島では日本人の定住化が進められ、産業として1880年ごろから父島でのコーヒー栽培が始まりました。しかし、台風の被害に弱かったためサトウキビ栽培に変更されていきました。
サトウキビ栽培では土地に肥料を与えることをせず、古い耕作地を放棄して新たな耕作地をどんどん切り開いていきました。
1910年代になると、南洋群島産の砂糖の影響で砂糖の価格が下落していったため、代わりにカボチャが栽培されるようになりました。ビニールハウスが普及していなかったころには、本土で収穫できない時期に収穫される小笠原産野菜は貴重でした。
このように、小笠原諸島の外来植物の影響は、島々に住む人間の経済活動によって引き起こされていきました。1899年からは破壊された自然を回復しようと新たな開墾禁止と植林が行われましたが、外来植物のリュウキュウマツやモクマオウなどを植林したため、固有植物の回復にはつながりませんでした。
第二次世界大戦後のアメリカ統治下において、父島以外は無人島であった時代があります。この際、戦争中に空襲で消失したかつて在来種の森林だった地域に外来植物が広がっていきました。無人になり飼い主を失ったヤギやネコが、ノヤギ、ノネコとなっていったのもこのころです。
1968年6月に小笠原諸島は日本に返還されましたが、小笠原復興特別措置法による開発が進められたことも、さらに在来植物の生育地を狭める原因になりました。
固有種保全のために
優れた木材として乱伐されたオガサワラグワ、羽毛採取のために乱獲されたアホウドリ、食用に乱獲されたウミガメなど、開発により多くの固有種を失った小笠原諸島ですが、1910年からウミガメの保護・人工孵化と放流事業を開始し、1926年には学術保護林を指定。そのほか、外来種の駆除を実施するなどして固有種の回復に努めています。
しかし、元来生物のいない状態であった小笠原諸島で、さまざまな経路をたどってやってきた生物が独自の進化をした結果として固有種が生まれたのも事実です。現在の外来種による影響もその過程の一部であると考える向きもあります。
保全するにしろ、進化の過程と捉えるにしろ、人間の手が入った時点でそれ以前の状態には戻らないということは大切な事実でしょう。