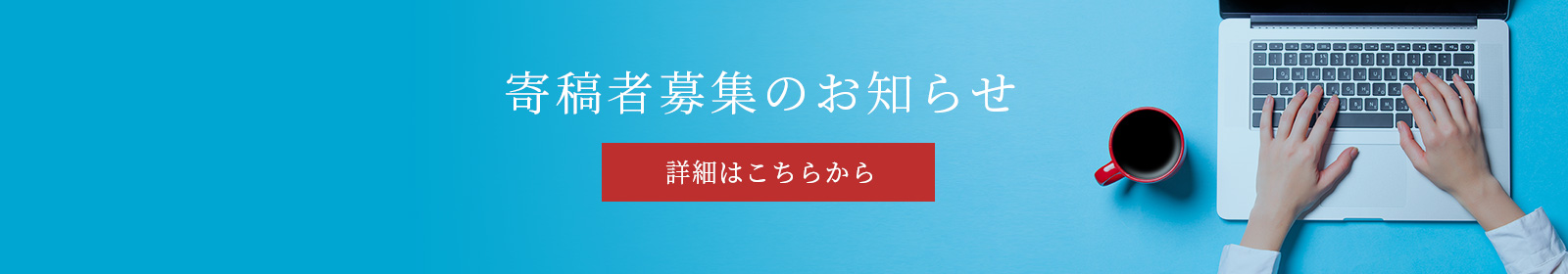この記事の目次
桐たんすにデメリットはあるの?

桐たんすとは
桐たんすは、防湿・防カビなどの機能性が高い桐を素材とした衣類を収納する日本の伝統的な家具です。湿度の高い日本では、古くから大切な品物を保管する収納箱には桐が使用されてきました。これは、桐が湿気によるカビや劣化を防ぐ優れた素材だったためです。
江戸時代半ばになると、綿織物や絹織物の生産が増え高級呉服が大衆化していきます。この流れのなかで着物の収納家具としてたんすが生まれました。とりわけ優れた機能性を持つ桐は最適な素材として使用され、桐たんすとして普及していきました。
全国には、さまざまな伝統工芸品としての桐たんすがあります。
- 加茂桐たんす
- 名古屋桐箪笥
- 大阪泉州桐箪笥
が特に有名で、これらについてはそれぞれ後ほど詳しく解説していきます。
桐たんすの特徴
材質が均一でゆがみが発生しにくい
家具に使用される他の様々な木材と比較すると、桐は伸縮やゆがみなどが発生しにくく狂いが少ない材質です。このため桐たんすは長期間使用しても変形が少ないと言われています。
軽量で持ち運びがしやすい
桐の構造はスポンジに似ていて、空気の層が多いことから他の木材に比べて軽量です。このため桐たんすは持ち運びがしやすくなります。
湿気を防ぎ気密性が高い
桐は湿度に敏感に反応する素材で、調湿機能にとても優れています。具体的には、外気の湿度が高くなると膨張して隙間をふさぐことで湿気の侵入を防ぎます。逆に、外気が乾燥していると収縮して湿気を発散し通気を良くします。この気密性の高さのおかげで内部の湿度を一定に保つことができるのです。
火災に強い
桐の吸湿性の高さから、火災時に水をかけて水分を含ませると、膨張して内部への熱伝導が少なくなります。桐たんすの外側が焼け焦げていても中の着物は無事だったケースもあるほどです。
虫を寄せつけない
桐には防虫効果のあるタンニンなどの成分が含まれているため、害虫を寄せ付けにくい特徴があります。このため桐たんすは衣類を害虫から守ってくれます。
以上のような理由から、桐たんすは高温多湿の日本において大切な衣類の収納に適しているな家具と言えるでしょう。
また、変形やゆがみが少なく長期間にわたって使用ができる点や、古くなって汚れても表面を削るなどの修理が可能な点は、モノを大切にする日本の文化とも馴染むといえるのではないでしょうか。
置き場所に注意が必要
桐たんすのデメリットとしてまず思い付くのはその大きさと費用ですが、これら以外にも注意が必要な点があります。それは置き場所です。
例えば冷蔵庫を設置する場合、後方と左右に数センチの空間を持たせるのがよいとされていますが、これは桐たんすも同様です。通気性を確保してカビなどを防ぐために後方に余裕を持たせると、思ったよりも部屋のスペースを占領してしまいます。また、湿気や太陽光を避けられる場所に置くほうが好ましいため、おのずと配置できる場所は限られてしまいます。
さらに、湿気が少ない場所に配置できたとしても、防虫剤や湿気取りをこまめに取り替えるなど維持の手間も必要です。万能に見える桐たんすにもデメリットはあるのですね。
桐たんすの修理やリメイクにかかる料金はどのくらい?
桐たんすには多くの嬉しい特徴がありつつも、維持にはそれなりの苦労がともなうことが分かりました。そこで、ここからは修理やリメイク、カビの除去にかかる料金について見ていきたいと思います。
修理・リメイク
購入した頃の桐たんすの魅力をできるだけ回復させる修理や、デザインを大きく変えるリメイクは、一般的にそのどちらとも新品を作る作業より手間がかかります。
これは、清掃はもちろんのこと、傷みの箇所を漏れなく確認して分解した後に木材などの補修・交換を行い、それが終わったらもう一度組み立て直すという手間がかかるからです。
あくまで一例ですが、料金としては、もっとも安くて5万円から高いと15万円程度、金具が多く使われている時代のたんすであれば、10万円から最大で20万程度かかる場合もあります。
カビ
から拭きで対処しきれないほどのカビが発生・定着してしまった場合も専門的な処理が必要になります。このケースでは一般的に、洗いだけではなく、カンナで削ってカビ菌自体を除去する作業が行われます。
カビの除去そのものにかかる料金は2万円から3万円前後ですが、削りなどを含めると最低でも5万円、目安としては10万円程度と考えた方がよいでしょう。
新潟県加茂市の伝統「加茂桐たんす」

加茂桐たんすとは
加茂桐たんすとは、新潟県加茂市で作られる桐たんすのことです。手作業による伝統的な高い技術と優れた品質は、加茂の匠の中で代々受け継がれてきました。1976年には伝統工芸品として指定もされました。
「日本一の桐たんす」と呼ばれるゆえん
「日本一の桐たんすのまち」と呼ばれている新潟県加茂市では、全国の桐たんすのうち約70%が作られています。加茂地域で作られ始めたのは1780年代の江戸中期からです。
その後の1820年頃には桐たんすは船積みされ、近くの加茂川から信濃川に出て新潟や東北方面へも進出していくようになります。
全国的に加茂桐たんすの認知度が高まったのは江戸末期以降で、遠く北海道へも出荷されるようになり販路を広げていくことになります。
加茂桐たんすは、高い技術力により桐たんすの持つ特性を活かしてあり、白い艶と美しい木目の色合い、木肌の温もりなどの特徴を持っています。
加茂総桐箪笥 板盆12枚衣装箪笥「藍山」3尺5寸3分幅 四方丸大洋衣装/総板盆12枚/本漆蒔絵前飾金具
経済産業大臣指定「伝統工芸品 加茂桐箪笥」の技法を受け継ぐ伝統工芸士が製作する高級桐たんすです。
扉の中には板盆が12枚あり、開けた際に着物を見分けやすいうえ、帯締めなどの小物整理用のお盆は移動や高さ調整もできるなど使いやすさを考えた逸品です。
サイズは、幅107cm、高さ150cm、奥行48.5cm。本体の厚みは24mmで国産桐を100%使用しています。「四方丸大洋衣装」という言葉は、以下の用語の組み合わせです。
- 四方丸:たんすの上下左右の四隅が丸く細工されていること
- 大洋:観音開きの大判の扉のこと
- 衣装:置物の衣類を主に収納する衣装たんすのこと
愛知県の伝統「名古屋箪笥」
名古屋桐箪笥とは
名古屋桐箪笥の起源は、1609年に徳川家康による名古屋築城が決定し、築城に携わった職人たちが城下町名古屋に定着して、たんすや長持を製造したことに由来します。
また、良質の桐の産地である岐阜県飛騨は名古屋から近く、素材を手に入れやすかったことで大きな発展へとつながりました。
1981年には国の伝統工芸品として指定を受け、「ものつくり名古屋」の伝統産業として一翼を担っています。
目が細かく仕上がりが美しい
名古屋桐箪笥の特徴は、「柾目」が表面に出ており、他の桐たんす産地のものと比べて目の細かい良質な材料を使用しているため、仕上がりがとても美しくて丈夫な点です。
一方、丸太の外側付近を切ると山形やタケノコ型の木目が現れますが、これは「板目(いため)」と呼ばれます。柾目は平行に目が均一に並んでいる分、割れにくく反りが少ないのですが、直径が大きい樹齢の長い大木からしか取れないため高価になっています。
名古屋桐箪笥の原材料は、伝統的に以下の3点を守っています。
- 木地は、桐とすること
- くぎはヒバ製あるいはこれと同等の材質のものを用いること
- 金具は、銅、銅合金または鉄製とすること
他にも名古屋桐箪笥には、他産地の桐たんすよりも幅が広く収納しやすい、本体が三つ重ねになっている、上置袋戸部分に金箔や漆塗蒔絵などで豪華絢爛な装飾が施されているものが多い、といった特徴があります。
大阪府の伝統「大阪泉州桐箪笥」
大阪泉州桐箪笥とは
大阪泉州桐箪笥は、江戸時代中期、農業をするかたわら副業として桐の木を使った木箱などの物作りが行われていたことが起源とされています。大阪府岸和田市や堺市周辺などの泉州地域で製造され、1989年には伝統工芸品として指定されています。
日本で初めてたんす作りの製造技術が確立されたのは大阪と言われており、堺から泉州地域へと産地が形成されるようになりました。
大阪泉州桐箪笥には20mm以上の厚みのある桐の無垢板が使用され、角を丸く削った胴丸の型のため全体的に重厚な雰囲気が特徴的です。桐材は1~2年かけて十分に自然乾燥させてから使うことで、アクが出ず美しさが保たれています。
矧ぎ加工・組み手加工による美と耐久性
また「矧ぎ加工(はぎかこう)」という柾目を揃えてつなぎ一枚の幅広い板にするという高度な技法を用いることで、より良質な桐の柾目を前面にそろえた繊細で優美なつくりとなっています。
その他には「組み手加工(くみてかこう)」という、使用する部材の先端に凹凸をつくることでくぎやねじを使わずに組み立てる、という高度な手法も取り入れています。これにより強度が増して、長年にわたって耐久性が高く保てる点なども特徴として挙げられます。
高い技術と熟練の技を駆使するために生産量は多くありませんが、大阪泉州桐箪笥は「日本最高峰」とも称されています。
桐たんすは日本の住環境において機能性と実用性を兼ね備えており、高い技術力を結集した美しく優れた伝統工芸品といえるのではないでしょうか。修理やリメイクにも費用がかかり、カビにも気を付ける必要はありますが、適切に管理すればきっとその魅力を存分に味わえるはずです。