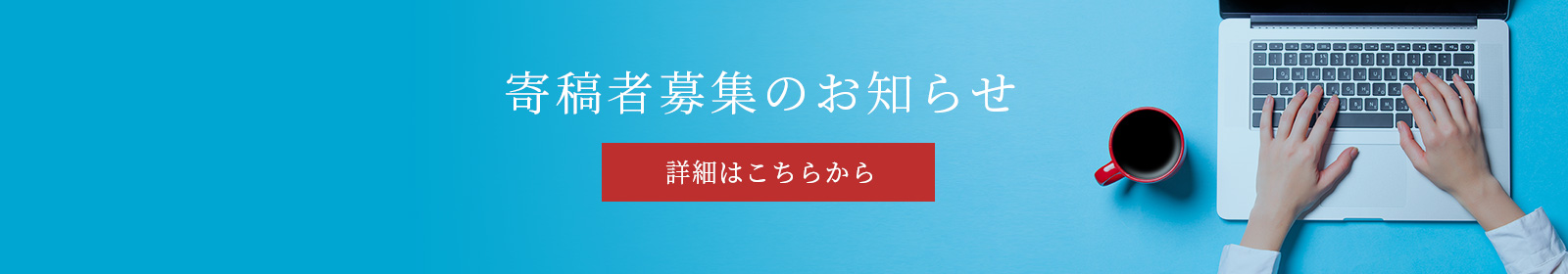この記事の目次
播州織とは

自然な色合いと肌触りの良さが特徴
播磨織は、兵庫県の北播磨地区で作られている綿織物です。
使用する糸を先に染め、染色された糸で布を織る先染織物である播州織は、北播磨地区で
- 考案
- 糸染め
- 織り込み
- 加工
の全てが行われた、高品質のものだけが名乗ることができます。
先に染めた糸で織布される播州織は、自然で鮮やかな色合いと肌触りの良さが特徴です。ハンカチなどの小物から洋服まで幅広く加工されており、国内先染織物のシェアは7割超。バーバリーやルイヴィトンに採用されるなど、国内のみならず海外からも高い評価を得ている織物です。
播州織の作り方
播州織の制作工程は、大きく分けるとデザイン・糸染・織り・加工となり、それぞれの事業者が分業制で作業を行っています。
- 手順1デザインテキスタルデザインの企画設計をする
- 手順2糸の染色購入した原糸を工場で染色する
- 手順3サイジング縦糸と緯糸に分けて作業が行われる。経糸は糸の長さをそろえたり、柄組をしたり、糊付けは織布の際に糸が切れにくいよう行われる。糊は仕上げの際に洗い落とされる。経糸も緯糸も、チーズ巻きなどの巻き方で巻かれ、織り機ですぐ使える状態にする
- 手順4織布多くの糸、さまざまな糸を使って布を織る
- 手順5加工さまざまな機能性加工を施す
豊富な機能性加工
播州織には、仕上がりをなめらかにしたり光沢を出すなどのさまざまな機能性加工が存在します。主な機能性加工は以下のとおりです。
標準加工
絹のような光沢を出して繊維の力を向上させる、シルプレシュランクーと呼ばれる加工法。
風合い加工
シルクのような仕上がりになる高級仕上げのチェリーソフトや、国産椿オイルを配合して優しい仕上がりになるツバキなど、加工法は多数。
表面感加工
横糸の配列を曲線に移動させて布に表情をもたせるクラッシュなど加工法は多数。
機能加工
形状安定加工・グレートキュアー・UV加工・防水加工など加工法は多数。
播州織の歴史
京都の西陣から技術が持ち帰られたことがルーツ
播州織の歴史は、1792年(江戸・寛政4年)に京都の西陣から、宮大工である飛田安兵衛氏が織機の技術を持ち帰ったことが起源とされています。
現在の西脇市周辺に位置していた播磨国(はりまのくに)では、糸を染めるために必要な水が豊富だったこともあり、1700年ごろから綿花が栽培され、草木で染料された生活衣類が作られていました。
飛田安兵衛氏が織機を制作したことで綿花を使った織物作りはさらに広まっていき、播磨織は農家の副業として発展していきます。その後の江戸時代末期には工場制手工業として確立され、1868年(明治元年)には、西脇・多可地域の綿布業者が70戸を超えるまでになりました。
 西陣織の魅力と特徴|美しさ・良さの秘密は作り方にあり
西陣織の魅力と特徴|美しさ・良さの秘密は作り方にあり 力織機の導入と鉄道網の整備により大きく発展
明治時代後期になると力織機が導入され、播磨織はさらなる発展を遂げていきます。
また、1906年(明治39年)の「第1回多可・加東・加西連合織物品評会」で、知事が訓話の中で播州織という言葉を用いたことから、その名が定着していきました。
鉄道網が整備された大正時代に入ると、播州織は全国的に知られるようになります。さらに、第一次大戦後にはそれまでの国内出荷から海外出荷をメインに転換。東南アジア向けの製品が多く作られるようになりました。
第一次黄金時代を経て国内指向に再転換
昭和初期には業者数が270軒超となり、第一次黄金時代を迎えます。第二次世界大戦後には、織機が一度”ガチャ”っと鳴れば1万円儲かるという「ガチャ萬」時代を迎え、多くの女性労働者が募集され、生産量はさらに拡大します。
米国・欧米諸国へ販路拡張と新製品の開発が行われましたが、昭和40年代になるとドルショックやオイルショックの影響を受けたため、国内の販路拡張へ力を入れるようになりました。その後の1987年に、播州織は生産量のピークを迎えます。
出荷量の減少とシステム刷新
平成に入ると、円高や海外製品の流入などさまざまな原因が重なって、国内出荷量・海外出荷量ともに減少が目立ちます。厳しい時代を迎えますが、時代のニーズに合った播州織を製作するために革新的な取り組みが行われます。
1995年(平成7年)からは毎年、東京や地元兵庫・大阪・神戸で見本市を開催し、2004年には、西脇市に本社を置く株式会社・片山商店を中心として考案されたシステム「アレンジワインダー」を開発。多くの種類の材質・太さの糸で織物を連続生産できるシステムは、翌2005年に「第1回ものづくり日本大賞」で内閣総理大臣賞を受賞しました。
さらに2006年には、播磨織の工場跡地を有効利用した播州織工房館や神戸のアンテナショップをオープンするなどの「播州織ファッション特区事業」という取り組みも行われています。
海外ブランドへの採用・現在へ
その結果、見事な色彩と自然な風合い、肌触りも良い播州織は、バーバリーやルイヴィトン・ダックスといった名だたる海外ブランドの生地として使用されていくことになるのです。
ファッションデザイナーであり播州織アーティストでもある玉木新雌氏が2004年に立ち上げたブランド「tamaki niime」は、経済産業省の「ザ・ワンダー500」に選定されています。播州織ならではの個性的な糸で織り上げられたショールは、海外からも高い評価を得ています。
歴史と伝統を備える播州織ですが、革新織機を使用し、多品種・小ロット・短納期など生産環境も整備され、日々努力が続けられながら時代に合った織物作りがされています。
播州織の人気商品

播州織 シャトル製ストール
優しい風合いの播州織ストールです。しっかり染めた糸が使われているので、やわらかな色合いなのに発色はしっかり。
どのストールも模様が細かで、ヴィンテージのシャトル織機で織り込まれている点も魅力。動きのあるデザインを楽しめます。
多彩な色を楽しめる肌触りの良いストールは、年齢や男女を問わず使うことができます。
ノービアノービオ・播州織ポケットチーフ
フォーマルウェアの専門店、ノービアノービオで販売されている播州織のポケットチーフです。
オーソドックスな紺地に白のドット柄ですが、優しい色合いの紺色なので、派手すぎることもなく品の良さが感じられます。
リバーシブルになっており、裏は白地に紺のドット柄。先染めの播磨織なので色落ちが少なく、ハンカチとしても使うことができるため、女性にもおすすめです。
長生堂・扇子・扇子袋・ハンカチセット・播州織ステッチ(赤/紺地)
結納品をはじめ、和装小物や扇子も扱っている、長生堂のオリジナル商品。
縦約22cm×横約40cmの扇子は、紺の地に赤で細かなステッチが入っているデザイン。上品で表情があり、表と裏でステッチが異なっているおしゃれな扇子です。
厚みがあり、機能性も抜群。シンプルながら存在感があり、年齢を選ばず使えます。
同様に赤でステッチされた扇子袋と、細かな縞模様がすてきな43cm×43cmのハンカチも付いているため、自分用はもちろん、贈り物にもおすすめです。
優しく豊かな色合いと肌触りが特徴の播州織。先染織物の国内シェアが7割超となっているので、気付かぬうちに播州織を身につけたり、触れたりしていることがあるかもしれません。
国内はもとより海外でも高い評価を得ている播州織は、近年新たなブランドが立ち上がったり、時代に合ったデザインを生み出したりなど、新たな取り組みが続けられています。